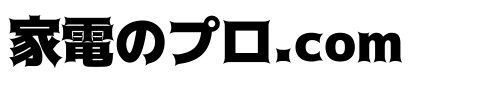目次
はじめに
寒い季節、頼りになるのが石油ファンヒーター。
ですが、朝スイッチを押した瞬間に「E1」や「E2」といったエラー表示が出て、動かなくなった…なんて経験はありませんか?
実は、こうしたエラーの多くは“故障ではなく使用環境や灯油の状態”が原因なんです。
そして同じように見えるファンヒーターでも、メーカーによって燃焼方式やエラーの出やすさがまったく違うのをご存じでしょうか?
-
ダイニチ
-
コロナ
-
トヨトミ
この3大メーカーの特徴を比較しながら、
「エラーを出さない正しい選び方」と「トラブル時の対処法」をわかりやすく解説します。
「壊れたと思って買い替える前に読む」
そんな冬のトラブル防止ガイドとして、ぜひ保存してお役立てください。
この記事を書いた人

もってぃー
・家電量販店勤務23年目
・白物家電を中心に営業で毎年1億の売り上げ実績
・家電アドバイザー資格取得
・「クラシル比較」などで家電記事を監修実績あり
石油ファンヒーターのエラー表示とは?
エラー表示は、内部のセンサーが異常を検知したときに点灯します。
つまり、「壊れた」ではなく、安全装置が働いたサインです。
主な発生原因は以下の3つ。
①点火不良(古い灯油・ノズル詰まり)
②燃焼異常(フィルター汚れ・吸排気不良)
③センサー異常(温度・炎検知・ファン回転など)
それぞれのメーカーによって構造や燃焼方式が異なるため、エラーの傾向にも特徴があります。
ダイニチ(DAINICHI)の特徴とエラー表示
特徴
ダイニチはブンゼン式燃焼方式を採用。
点火スピードが速く、静音性に優れたモデルが多いのが特徴です。
一方で、灯油の品質に非常に敏感。古い灯油はエラーの原因に。
<主なエラーコード>

ブンゼン式燃焼方式とは?(ダイニチが採用)
仕組みをひとことで言うと…
「灯油を気化させて空気としっかり混ぜ、きれいに燃やす方式」です。
仕組みの流れ
① 灯油を気化皿(バーナー部)で温めてガス状にする
→ ヒーター内部の気化器が、灯油を霧状ではなく“蒸気”に変えます。
② ファンで空気を送り込み、灯油の蒸気と混合(混気)
→ 空気と灯油ガスを混ぜて、燃焼に理想的な状態にします。
③ 点火ヒーターで一気に燃焼開始!
→ プラグで火がつくと、安定した“青い炎”が立ち上がります。
炎センサーで燃焼状態を常時監視
→ 炎が安定していないと自動停止。安全性が非常に高い構造です。
ダイニチホームページより引用
ブンゼン式のメリット
① 点火が速い
灯油を気化してから燃焼するため、点火まで約35〜40秒とスピーディ。
② ニオイが少ない
完全燃焼に近い状態で燃えるので、点火・消火時の臭いがほとんどない。
③ 燃焼が安定
空気との混合比を自動制御するため、炎が安定しムラが少ない。
④ クリーン
ススやCO(一酸化炭素)が出にくく、室内の空気を汚しにくい。
デメリット・注意点
① 灯油品質に敏感
古い灯油や水分が混じると、気化器が詰まって「E1」「E2」エラーに。
② 定期清掃が必要
フィルターや吸気口のホコリでも燃焼バランスが崩れる。
③ 消費電力がやや高め
点火ヒーターや気化ファンを使うため、初期の電力消費は多い。
現場の実感
ダイニチのヒーターは「朝すぐ温まる」点が好評。
ただし、前年の灯油を使うとE1エラーが出やすく、点検に持ち込まれることが多いです。
逆に言えば、新しい灯油+定期清掃さえしていれば非常に優秀な燃焼方式です。
コロナ(CORONA)の特徴とエラー表示
特徴
コロナはポンプ噴霧式燃焼。
灯油を細かく霧状にして燃焼させるため、
電気代が安く燃費にも優れています。
ただし、長期使用による電極の汚れやモーター摩耗に注意。
<主なエラーコード>

ポンプ噴霧式燃焼方式とは?(コロナが採用)
一言で言うと…
「灯油をポンプで霧状に噴射し、空気と混ぜて燃やす方式」です。
燃焼のイメージは「スプレー缶に火をつけたような霧状の炎」。
ダイニチの“気化式(ブンゼン式)”とは異なり、液体の灯油を直接噴霧して燃焼させるのが大きな特徴です。
仕組みの流れ
① ポンプで灯油を一定量ずつ吸い上げる
➡ ファンヒーター内部の電動ポンプが、タンクから灯油を送ります。
② ノズルから霧状に噴射
➡ 微細な霧(ミスト状の灯油)を燃焼室へ均一に噴き出します。
③ 点火ヒーターで着火し、炎を維持
➡ 空気と混ざりながら安定燃焼。赤みのある柔らかい炎が特徴です。
④ ファンで温風を送り出す
➡ 焼けた熱交換器に風を当てて、温風として部屋全体を暖めます。
ポンプ噴霧式のメリット
①燃費が良い
ポンプが必要な分だけ灯油を供給するので、省エネ性能が高い。
②構造がシンプル
故障が少なく、長期使用にも比較的強い。
③電気代が安い
点火ヒーターを短時間しか使わないため、消費電力が低い。
デメリット・注意点
① 点火がやや遅い
気化式に比べて点火まで40〜60秒ほど時間がかかる。
② ニオイが出やすい
点火・消火時に霧状の灯油が残り、においが立ちやすい。
③ 定期清掃が必要
噴霧ノズルが詰まるとE1(点火不良)が出やすい。 電極・ノズルの摩耗長年使用すると噴霧精度が落ちて燃焼ムラが出る。
トヨトミ(TOYOTOMI)の特徴とエラー表示
特徴
トヨトミは気化式(ダブルクリーン)を採用。
燃焼効率が高く、持ち越し灯油にも比較的強い構造です。
ただし、安全装置が敏感で、環境要因による誤作動も起こりやすい傾向があります。
<主なエラーコード>

トヨトミの「気化式(ダブルクリーン)燃焼方式」とは?
一言で言うと…
「灯油を芯で吸い上げ、熱で気化させて燃やす方式」です。
もともとトヨトミは芯式ストーブ(昔ながらの反射式ストーブ)の技術を持っており、
そのノウハウをファンヒーターに応用して開発されたのが、この気化式(ダブルクリーン)です。
ダブルクリーンの仕組み(2段燃焼構造)
トヨトミの“ダブルクリーン”とは、名前の通り二段階で燃焼を行う構造を指します。
トヨトミホームページより
① 第1燃焼:気化燃焼ゾーン
-
灯油を「ウィック(芯)」が吸い上げ、ヒーターで加熱。
-
灯油が気化ガスになり、一次燃焼で火がつく。
-
この段階でほぼ完全燃焼に近い状態になります。
② 第2燃焼:再燃焼ゾーン
-
一次燃焼で出た微量の未燃ガスを、上部の高温空気で再燃焼。
-
煙やニオイを大幅にカット。
-
これが「クリーン燃焼」の秘密です。
結果:点火・消火時のニオイが少なく、ススもほとんど発生しません。
[タンク]→[芯が灯油を吸い上げ]→[気化器で蒸発]→[一次燃焼]→[再燃焼]→[温風ファン]
ダブルクリーン方式のメリット
① クリーン燃焼
二段燃焼でスス・ニオイ・一酸化炭素をほぼゼロに。
② 環境変化に強い
柔軟剤・スプレーの香料にも比較的影響を受けにくい。
③ 灯油の持ち越しに強い
気化燃焼なので、やや古い灯油でも燃えやすい。
④ メンテナンス性
芯交換や内部清掃で長寿命。構造が比較的シンプル。
⑤ 安全性が高い
炎検知・酸素不足検知・過熱防止など安全装置が充実。
※使用できる残り灯油は日の当たらない冷暗所で保管し、保管期間1年以内のものに限ります。水が混入した不純灯油や変質灯油は使用できません。
デメリット
① 点火がやや遅い
ブンゼン式ほど即点火ではなく、約1分前後かかる。
② 芯の劣化
長期間使うと芯の吸い上げ性能が落ち、炎が弱くなる。
③ 初期消費電力
点火ヒーターで一時的に電力を使う。
④ メンテナンス要
3〜5年に一度、芯交換・内部清掃が理想。
現場の販売員コメント
トヨトミのファンヒーターは、ニオイが少なく静かで長持ちという声が多いです。
芯の交換で新品のように復活するので、長く愛用したい方にぴったり。
また、安全装置が非常に敏感で、家具や壁に近すぎると「E4高温エラー」が出るのも特徴です。
これは“壊れている”のではなく、“守ってくれている”証拠です。
現場で多いトラブル原因ベスト3
家電量販店の店頭で点検していると、
エラーの約半分は“使用環境”が原因です。
① 不良灯油(古い灯油)
-
前シーズンの残りやポリタンクに長期間保管した灯油は酸化・劣化。
-
水分や不純物で点火が不安定になり、E1・E2の原因に。
👉 対策:毎年必ず新しい灯油を購入。
② 柔軟剤・スプレーの使用
-
ファンヒーター付近でヘアスプレー・消臭スプレー・柔軟剤入り衣類を干すと、
その香料成分がフィルターやセンサーに付着。 -
センサー誤作動でE2・E9が表示されることも。
👉 対策:使用中はスプレー類を避け、周囲50cm以上あける。
③ フィルター・センサー汚れ
-
吸気口のホコリや静電気の付着が原因で異常検知。
👉 対策:月1回、掃除機で軽く吸うだけで十分。
修理持ち込みの約9割は「不良灯油+環境要因」で改善可能。
故障だと思っても、まず灯油と掃除をチェックしましょう!
まとめ:エラー表示は“壊れた”ではなく“守ってくれている”
石油ファンヒーターのエラー表示は、本体が安全を守るために停止しているだけのことが多いです。
焦らず、灯油・フィルター・環境をチェックしてみてください。
日々のちょっとした手入れで、冬を快適に過ごせます。